 浄土真宗宗祖親鸞の教えが書き記された「歎異抄」。おそらく世の中で最も読まれている宗教書だろう。歎異とは「違いを嘆くこと」。親鸞亡き後20数年を経て、聖人の教えとは異なった解釈が広まるのを嘆いた唯円が、「本願念仏」の本旨を後世永久に伝えるために書いたとされる。今も私たちを魅了してやまない代表的古典である。
浄土真宗宗祖親鸞の教えが書き記された「歎異抄」。おそらく世の中で最も読まれている宗教書だろう。歎異とは「違いを嘆くこと」。親鸞亡き後20数年を経て、聖人の教えとは異なった解釈が広まるのを嘆いた唯円が、「本願念仏」の本旨を後世永久に伝えるために書いたとされる。今も私たちを魅了してやまない代表的古典である。
ちくま学芸文庫の本書は明治学院大学名誉教授の阿満利麿が現代語訳と解説を担当。阿満氏は京大卒後、NHKに入局。その後、宗教学者へと転じたという経歴の持ち主で、宗教関係、特に法然と親鸞の教えに内在する原意をわかりやすく示した著書が多数。以前取り上げた角川書店の法然「選択本願念仏集」も同氏によるものだ。
さて「歎異抄」だが構成は全十八章から成っている。唯円が書を著すに至った理由を述べる序文から始まり、第一章から第九章では親鸞思想の要諦となる語録を紹介し、第十章から第十八章では誤った解釈や言動の数々を俎上に載せて親鸞の真意を教え諭す。そして最後は正しい信心への切なる願いを込めた結文で終える。
親鸞の教えとはどういうものなのか。それは法然の教えと同じであるといってもいいだろう。法然が「ただ南無阿弥陀仏と一心に唱えるだけで人は浄土へ行ける」と説いた「本願念仏」、そして「老少善悪のひとをえらばれず」「罪悪深重、煩悩熾盛の衆生をたすけんがため」と、弥陀の本願には老人も若者も、善人も悪人も、階級も貧富も関係ないという平等性が二人の共通した「思想」であった。
親鸞特有の解釈としては、よく「悪人」というキーワードが挙げられる。第三章の「善人なをもて往生をとぐ、いはんや悪人をや。しかるを世のひとつねにいはく、悪人なを往生す、いかにいはんや善人をやと」「悪人成仏のためなれば、他力をたのみたてまつる悪人、もとも往生の正因なり」のあたりである。
悪人とは悪事を働く人間を指すのか。では善行を重ねた者が報われないではないか。確かに法然は従来の思想では浄土に行くことが難しいと言われていた、人を殺す職業の武士も家畜や魚を殺す人も善悪は一切関係ないと説いた。しかし親鸞はさらに一歩押し進め、人間とは煩悩を絶対に消すことの出来ない生き物なのであり、いわば私欲にまみれた凡夫、悪人である、阿弥陀はそんな人間こそ救ってくれるのだと定義した。ここは少し難しい。この意味について訳者の阿満は「親鸞のいう悪人とは世間一般の道徳的な善悪ではなく、人間の中に潜む煩悩、エゴイズムであろう」と説明する。つまり「善」を持つものは「仏」しかいない。人間は全て「悪人」と言える。そんな利己的な性質を持つ人間こそ必ず仏になれると親鸞は言っているのだ。
また個人個人の心の持ち様にも深く入り込んでいる事にも注目したい。特に現代宗教はともすれば教祖崇拝、教団崇拝に力点が置かれる事が多いが、親鸞は生涯に渡って教団も弟子も持つことは無かった。孤高と呼ばれる由縁だ。信者がその理由を尋ねると親鸞は「わがはからひにて、ひとに念仏をまうさせふらはばこそ・・(第六章)」と、私の計らいで人を仏に導くことが出来るなら良いが、それは出来ない、専修念仏において人は阿弥陀仏の促しによってのみ仏になるのだから、わが弟子などということはまことに尊大だと答えている。
これは晩年よく言っていた「弥陀の五劫思惟の願をよくよく案ずれば、ひとへに親鸞一人のためなりけり」の考えと通ずる。他人を救うことはできない、自分がこれまでやってきた事は自分自身のためだったと親鸞はいう。一見利己的で突き放したようにも聞こえるが、「念仏とは他者のためではなく、自分が仏になるためのもの」「死後、浄土の世界で自分が仏になって多くの人を救えばよい」を聞くと何となく納得がいくだろう。信心とは一人一人のものなのだ。普段の生活の中で各々が念仏を唱えればいいのだ。出家する必要もないし、凡夫には到底無理な苦行をする必要もない。ただひたすら信じて唱えれば阿弥陀の力によって、自身の中にある「信心」が萌芽し、前進出来るのだと言う。
物質と情報が大量に溢れGNPでも世界有数を誇る経済大国日本。宗教とは最も縁遠い時代のようにも思える。しかし人生は順風満帆なことばかりではない。むしろ理不尽なことの方が多い。世界を見渡してみれば、殺人事件、交通事故、地震、津波などの自然災害、原発などの人的災害が絶え間なく起きている。私たちは自分ひとりの力では如何ともし難い災難や不幸に直面した時、どうすれば良いのかわからなくなる。そしてやり場の無い怒りや絶望、無力感に苛まれる。肉親や愛する人を失った時はなおさらだろう。
そんな苦しいときに人は「矛盾や不条理を自覚した時に「仏」というあり方に惹かれる」と著者はいう。そして人は人生の安らぎ、ゆとり、自信、余裕を求めて「無碍の一道」を歩み出す。弛まない「信心」の結果、一人一人の幸せを見出すのである。

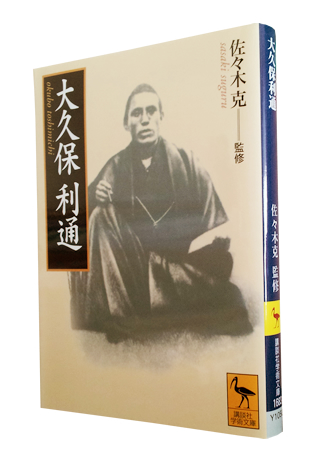
 『西郷隆盛 南洲翁遺訓』 (角川ソフィア文庫) 西郷 隆盛、猪飼 隆明 1890年(明治23年)発行
『西郷隆盛 南洲翁遺訓』 (角川ソフィア文庫) 西郷 隆盛、猪飼 隆明 1890年(明治23年)発行 本書は、
本書は、